レオンハルト・オイラー
| レオンハルト・オイラー | |
|---|---|
 Leonhard Euler | |
| 生誕 | 1707年4月15日 |
| 死没 | (1783-09-18) 1783年9月18日(76歳没) [OS: 1783年9月7日] |
| 研究分野 | 数学、天文学 |
| 研究機関 | ロシア科学アカデミー プロイセン科学アカデミー |
| 出身校 | バーゼル大学 |
| 博士課程 指導教員 | ヨハン・ベルヌーイ |
| 主な指導学生 | ジョゼフ=ルイ・ラグランジュ |
| 主な業績 | オイラー図、オイラー数、オイラー積分、オイラー線、オイラーの公式、オイラーの等式、オイラーの五角数定理、オイラーの定数、オイラーの定理 (数論)、オイラーのφ関数、オイラー標数、オイラーの分割恒等式、オイラー法、オイラー予想およびオイラー路の発見 |
署名 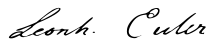 | |
プロジェクト:人物伝 | |
レオンハルト・オイラー(Leonhard Euler, 1707年4月15日 - 1783年9月18日)は、18世紀の数学者・天文学者(天体物理学者)。
18世紀の数学界の中心となり、続く19世紀の厳密化・抽象化時代の礎を築いた[1]。数学者としての膨大な業績と、後世の数学界に与えた影響力の大きさから、19世紀のカール・フリードリヒ・ガウスと並ぶ数学界の二大巨人の一人とも呼ばれている。
目次
1 概要・生涯
2 業績
2.1 解析学
2.2 数論
2.3 幾何学
2.4 数理物理学
2.5 関数概念の導入
3 その他
4 参考文献
5 著作
6 関連項目
7 外部リンク
概要・生涯
1707年、スイスのバーゼルに生まれる。ヨハン・ベルヌーイによって才能を見出されたことと、オイラー自身が数学に興味を抱いていたことから、数学者になる道を選んだ。オイラーの父も数学の教育を受けた人物であったが、オイラーには自分の後を継いで牧師になることを望んでいた[1]。
1727年、オイラーはサンクトペテルブルクの科学学士院に赴任した[1]。この地でダニエル・ベルヌーイの同僚となり、バーゼル問題を解決したことで有名になった。しかし、エカチェリーナ1世の突然の死でロシアは政情不安となり、視力の悪化も伴って、研究生活は不安定になった。
1741年、プロイセン王国のフリードリヒ2世の依頼でベルリン・アカデミーの会員となり、ドイツへ移住した[1]。その業績からフリードリヒ2世に「数学のサイクロプス(単眼の巨人)」と賞賛される(右目を失明していたため)。彼は『無限解析入門』 "Introductio in analysin infinitorum" と『微分学教程』 "Institutiones calculi differentialis" という2冊の数学書を出版した。
また、オイラーはアルンハルト=デッサウ公女の教育のために科学への入門書を執筆し、その後、『自然科学の諸問題についてのドイツ王女へのオイラーの手紙』 "Lettres à une Princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie" として出版された。この本は欧米で一般の読者を対象にした科学書として広く読まれ、オイラーの最も有名な著書となった。当時ベルリン・アカデミーには、ヴォルテールもいたが、二人が親密になることはなかった。
エカチェリーナ2世が帝位についたことで、1766年ごろオイラーは再びサンクトペテルブルクに戻った[1]。1738年ごろより視力が低下し[1]、1771年ごろ(1766年とする説もある)には両目を完全に失明したものの、その後も研究意欲が衰えることは全くなく[1]、彼は論文の執筆を口述筆記に頼りながら、1783年に76歳で亡くなるその日まで精力的な研究活動を続けた。墓はアレクサンドル・ネフスキー大修道院にある。
業績
解析学

スイスの第6次紙幣の10フラン紙幣
解析学(無限小解析)においては膨大な業績があり、微分積分の創始以来もっともこの分野の技法的な完成に寄与した。級数や連分数・母関数の方法・補間法や近似計算・特殊関数や微分方程式・多重積分や偏微分法など、古典的な解析学のあらゆる領域において基礎から応用にいたる広い業績があり、自身の発見を教科書を通し広く一般に普及させた。
膨大な量のため、彼の解析学における仕事、言わば公式一つ一つが完全に伝わっている訳ではなく、新たな公式の発見とされたことが実はオイラーの発見の再発見に過ぎなかった、ということがしばしば起きている。
また、彼の名前は指数関数と三角関数の関係を与えるオイラーの公式・オイラー=マクローリンの和公式・オイラーの微分方程式・オイラーの定数などに残っている。
さらに複素数の変数を積極的に用いて、解析学に限らず数学全分野に大きな業績を残した[1]。
数論
フェルマー以降進展がなかった整数論において、ラグランジュの出現までほぼ一人で研究し続け、二次形式や原始根・フェルマーの小定理の拡張など、数々の功績を残した。現在でも、数論的関数の一つであるオイラー関数(オイラーのφ関数)に彼の名前が残っている。
またゼータ関数を初めて扱い(ゼータ関数の名称はリーマンによる)、後に解析的整数論の重要な主題となる重大な結果を得た。彼は1735年にζ(2)=π2/6を求めることに初めて成功し、さらにζ(4) = π4/90、ζ(6) = π6/945、ζ(8) = π8/9450、ζ(10) = π10/93555、ζ(12) = 691π12/638512875 を求めた。また、1737年にはゼータ関数と素数の関係を表すオイラー積の公式を発見し、素数の逆数の和が発散するという新たな結果を得た。さらに超人的な数学的直感に基づいてゼータ関数の負の数における値に意味付けを与えたが、これは後に数学的に正当化された。数の分割の理論においては、母関数の方法の応用が著しく、五角数定理をはじめ様々な組み合わせ論的、あるいは楕円関数論的な恒等式を得た。
幾何学
幾何学においては、位相幾何学のはしりとなったオイラーの多面体定理(ただしオイラーは証明を与えていない)や「ケーニヒスベルクの橋の問題」が特に有名である。特性類の一つであるオイラー類は本質的にこのオイラーの多面体定理によって特徴付けられるものである。「ケーニヒスベルクの橋の問題」は一種の一筆書き問題であるが、オイラーはこれに取り組んで一筆書きが可能になるための必要十分条件を求めた。これはグラフ理論の起源となり、今日では一筆書き可能なグラフはオイラーグラフと呼ばれる。解析幾何学でも古代ギリシャのアポロニウスによる円錐曲線の理論を解析幾何学的手法によって近代化をはかっている。
数理物理学
数理物理学では、ニュートン力学の幾何学的表現を解析学的に修正して、現代的なスタイルに変更した。
彼は1736年に初めて力をはっきり定義し、解析的な形で運動方程式を与えた。
それ以後、この定式化に基づいて振動弦の問題を論じ、また地球の章動の研究において運動方程式による3体問題の定式化を行った。
そして1755年には流体力学の基礎方程式(連続方程式と運動方程式)を導いて体系化した。
さらに1760年には剛体の力学を論じ、剛体に固定した運動座標系を導入してオイラーの運動方程式を得、これを発展させた。剛体の方位を規定する3つの角は「オイラーの角」と呼ばれている。
だが、彼は1760年代までニュートンの重力理論を容認できず、デカルトの充満理論・エーテル理論に固執した。
その他、変分法に関する業績も多い。
関数概念の導入
ライプニッツによって定義された関数を初めてy=f(x)の形で表したのもオイラーである。
このような近代的関数の概念は1748年に導入され、物理学など応用方面でも使いやすいものとなった[1]。
その他
オイラーは人類史上最も多くの論文を書いたと言われる数学者であり、並の数学者が一生かかって執筆する量の論文(800ページ以上)をオイラーは毎年のように生産し続けていたとも言われる。
彼の論文は5万ページを超える全集にまとめられて、1911年から刊行され続けているが、その全集は100年以上たった今日でも未だに完結していない[1]。
1980年~2000年にかけて流通していたスイスの第6次紙幣の10フラン紙幣にはオイラーの肖像を見ることができる。
参考文献
- ^ abcdefghij 日本数学会編『岩波数学辞典 第4版』、岩波書店、2007年、項目「オイラー」より。ISBN 978-4-00-080309-0 C3541
著作
- おいれる 『不定解析論 おいれる代数学 整数論ノ一部』 林鶴一・小野藤太訳、大倉書店〈数学叢書 第18編〉、1914年。
- レオンハルト・オイラー 『オイラーの無限解析』 高瀬正仁訳、海鳴社、2001年6月。.mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
ISBN 4-87525-202-1。 - レオンハルト・オイラー 『オイラーの解析幾何』 高瀬正仁訳、海鳴社、2005年11月。
ISBN 4-87525-227-7。
関連項目
- オイラーの公式
- オイラーの等式
- 数論におけるオイラーの定理
- 微分幾何学におけるオイラーの定理
- 平面幾何学におけるオイラーの定理
- ゴールドバッハ・オイラーの定理
- オイラー予想
- バーゼル問題#オイラーの解法
オイラー積分
- ベータ関数
- ガンマ関数
- オイラー=ラグランジュ方程式
オイラーの運動方程式
- オイラーのコマ
- オイラー力
- オイラー角
流体力学におけるオイラーの方程式(非粘性流体)
- → ナビエ-ストークスの式(粘性流体)
- ベルヌーイ・オイラーの仮定
- 座屈応力に関するオイラーの式
- オイラー法
- オイラーの多面体定理
- オイラー円
オイラー路(オイラーグラフ、準オイラーグラフ)- オイラー線
- オイラー図
- オイラーのφ関数
- オイラーの和公式
- オイラー積
- オイラーの分割恒等式
- オイラーの五角数定理
ネイピア数(オイラー数と呼ばれることがある)- オイラー数
- オイラーの定数
- オイラー標数
- オイラー素数
- オイラー (小惑星)
外部リンク
O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., “Leonhard Euler”, MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews, http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Euler.html .
The Euler Archive オイラーの原論文を閲覧可能- Google logo for Leonhard Euler
レオンハルト・オイラー - Find a Grave